
「冒険する組織」とは?権力や報酬に頼らない組織づくりのヒント【前編】
「PeaCAL」は、ピーティックスが全国の地域イベント・コミュニティおよびその主催者を支援するメディアです。イベント主催者の活動を発信し、相互のナレッジ共有を促進することで、地域コミュニティの活性化を目指しています!
この「PeaCAL Talk」シリーズでは、地域に根ざしたコミュニティ・イベントの主催者に焦点を当て、その活動や経験を深く掘り下げていきます。
今回は、『冒険する組織のつくりかた』の著者であり、人と組織の経営コンサルティングファームMIMIGURIの代表を務める安斎勇樹さん、そして10年以上にわたってボランティアコミュニティTEDxHamamatsuを運営している河口哲也さんをお招きし、「変化し続ける組織のあり方」について語っていただきました。
企業のマネジメントは長年、「軍事的な戦略」の影響を受け、トップダウン型の組織運営が当たり前とされてきました。
しかし、時代は変わりつつあります。転職や副業が一般的になり、組織に属すること自体が目的ではなくなってきました。働くことの意味が問われる中で、企業もまた「どのような組織であるべきか?」を見直す必要に迫られています。
組織をどう持続させるのか、どうすればメンバーの自己実現を支えられるのか——そのヒントが詰まった対談内容を、ぜひ最後までお読みください。
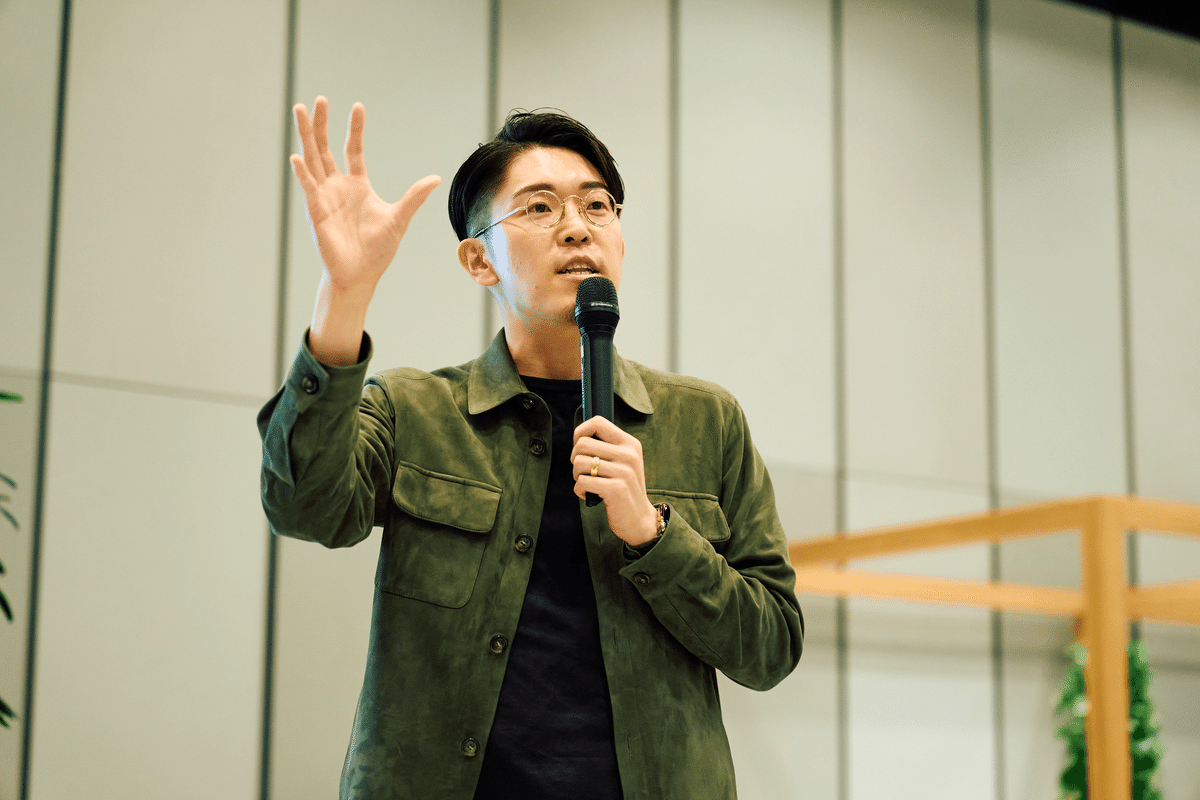
安斎 勇樹
株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO
東京大学大学院 情報学環 客員研究員
1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『冒険する組織のつくりかた:「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』『問いのデザイン』『問いかけの作法』などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

河口 哲也 Tesuya Kawagushi
Rf代表/TEDxHamamatsu オーガナイザー
1972年生まれ。静岡県浜松市出身。
TEDxHamamatsuを2015年から開催する傍らで、浜松市などで起業家支援施設の立ち上げなどに携わる。
組織やチームのコミュニケーションのあり方を問い直しつつ、コミュニティや、場づくりのサポートを行う。
2021年よりレゴ®シリアスプレイ®メソッド トレーニング修了認定ファシリテーターとしても活動中。
「冒険する組織」とは?
ピーティックス 山宮(以下、山宮):
本日は、お二人と「権力や報酬に頼らない組織づくり」をテーマにお話ししていきたいと思います。
まず最初に、安斎さんにお伺いしたいのですが、新刊『冒険する組織のつくりかた』で提唱されている「冒険する組織」とは、具体的にどのような組織を指すのでしょうか?
MIMIGURI Co-CEO 安斎勇樹さん(以下、安斎さん):
「冒険する組織」と聞くと、「危険を冒してリスクを取る組織」というイメージが湧くかもしれませんが、この本では、軍事的な組織との対比として考えています。これまでの経営やマネジメント、組織論は、戦争のメタファーを多用してきました。
戦略や戦術といった言葉もその一例で、実は1930年代までは企業経営で「戦略」や「戦術」といった言葉は使われていなかったんです。1940年代の戦争を経て、軍事的な統率の方法が企業マネジメントにも応用されるようになり、戦略、戦術、ロジスティクスといった軍事用語が企業経営の中に根付いていきました。
これが当たり前のように受け入れられてきた背景がありますが、Z世代の若い人たちにこの話をすると、「気持ち悪い」と捉えられるんです。
かつてのキャリア観は、「1つの会社で長く勤め、出世する」「感情を抑え、職場に個人的な感情を持ち込まずに働く」ことが前提でした。しかし、今の時代は人生100年時代といわれ、転職や兼業、副業が当たり前になり、働くことの意味や目的が変わってきています。
そうした変化の中で、組織のあり方も変わりつつあります。これまでの組織は、企業の成功が最優先で、従業員はそのための駒として機能する存在でした。しかし、今は個人のキャリア観も変化し、企業も明確なビジョンを持たないと人がついてこない時代です。
この本では、漫画『ONE PIECE』の麦わらの一味を例に挙げています。彼らには共通の目標(ワンピースを見つける)がありながらも、それぞれに個別の夢や目標がある。ゾロは世界一の剣豪を目指し、ナミは自分の手で世界地図を描きたい、チョッパーは万能薬になりたい。
それぞれの目標が、組織全体の目標と対立するのではなく、相互に影響し合いながら共存している。このように、個人の好奇心や価値観と組織の目標がフラットに共鳴する関係こそ、『冒険する組織』の本質だと考えています。
山宮:
Z世代と僕たち世代の価値観の違いをすごく感じますね。実際に、若い世代の意見を聞きながら進めないと危ういなと感じる場面も多いです。今の安斎さんのお話を聞いて、改めて納得しました。
河口さんはTEDxHamamatsuなど、さまざまなボランティアコミュニティを運営されていますが、そうした組織を存続させるためにどのようなことを大切にし、どんなアクションをとっていますか?
TEDxHamamatsu 河口哲也さん(以下、河口さん):
「冒険する組織」は、TEDxの運営にも通じる部分が多いと感じます。関わる人たちのモチベーションや動機はさまざまですが、それを尊重しながらも、運営に必要なルールとのバランスを取ることが求められます。
TEDxHamamatsuのような、権力や報酬に頼らないボランティアコミュニティでは、各人のやりたいことや自己実現を支援する仕組みが大事になってきます。ただ、組織としての目標もあるので、それらをどう両立させるかは常に悩みながら考えています。
惰性を防ぎ、自律を育てる仕組み
山宮:
なるほど。もう少し話を広げて、権力構造を超えた組織、つまり自律的な組織が形成されるためには、どのような環境や仕組みが必要なのでしょうか?
河口さん:
僕たちのTEDxHamamatsuでは、毎年の活動の終わりに「解散宣言」をして、一度解散するんですよね。その理由としては、ボランティアなので、一度みんなを元々優先順位の高い場所(仕事や家庭など)に戻してあげるべきだと考えていたからです。そして、「またやりたかったら戻ってきてね」という形を取っていました。
でも、今日改めて思ったのは、「それって本当に正解なのかな?」ということです。
例えば、「まだ探求したいことがある」と思っている人にとっては、わざわざ解散して関係を断ち切る必要はないかもしれない。僕は「一度区切りをつけて戻してあげることが、みんなにとっての優しさだ」と考えていたんですけど、それが果たして最善だったのか、ちょっと疑問に思い始めました。
やりたいことがある人は、そのままスムーズに続けられるような仕組みがあってもいいのかもしれません。
安斎さん:
運営側としては、「なんとなく続けてしまう惰性」を防ぐために、あえて解散という儀式をやっていたわけですよね。でも今、それが必ずしも最適解とはいえないかもしれないと思い始めている。
実際、解散した後でもまた戻ってくる人はいるわけで、そういう人たちは「一度解散することで、自律的な参加を選んでいる」ともいえますよね。
河口さん:
そうですね。ただ、コロナ前と後で、人の動きが変わったのも影響していると思います。
コロナ前は、解散しても結局また戻ってくる人が多くて、「去年と同じようにやればいいじゃん」という感じで、ある意味、先輩のやり方をそのまま踏襲するケースが多かった。
でも、コロナ後は毎年メンバーの半数以上が入れ替わるようになった。その心理的な変化は、僕も正直よく分かっていないんですが、大きな変化があったことは間違いないですね。
安斎さん:
コロナ前後で、日本中の「なんとなく続いていたこと」が見直されたと思うんです。多くの人が、「本当にこれを続ける必要があるのか?」と立ち止まって考える機会を持った。
例えば、なんとなく出社していたけど、リモートで十分じゃんとか、イベントはオフラインじゃないとダメだと思っていたけど、オンラインで成立するじゃんとか。惰性で続けていたことに疑問を持つようになった。結果として、本当に必要だと思えば続けるし、そうでなければ変える、という社会的合意が形成された。
そして、これは「権力」と「惰性」が密接に関係していることを示しているんですよね。権力者が強権を振るったわけじゃなくても、長年の習慣や慣例が、「続けるのが当然」という圧力になり、ノーと言えなくなる。
だから、「解散」という仕組みを通じて、一度バトンを本人に戻すのは、ある意味で権力の固定化を防ぐシステムとして機能していたと思います。それって、空気を読んで「やらなきゃいけない」と思い込んでしまうことへの抵抗でもある。飲み会は行かなくてもいいよ、と明文化するのと同じように、「やりたければ戻ってくればいいし、そうじゃなければ自由にしていい」というルールがあることで、自律性が保たれるのかもしれないですね。
「冒険する組織」における報酬のあり方
山宮:
TEDxHamamatsuには初年度から毎年関わっているんですが、たしかに解散という仕組みがあることで、安斎さんの言う「軽度な自律」が生まれているのかもしれないなと感じます。ある種、解散があることで自分の意思で戻ってくるという感覚が持てるのかなと。
改めて、報酬や対価というものについて考えると、それがどこに存在するのかが重要になってきますよね。安斎さんが提唱する「冒険する組織」にとって、報酬とはどのようなものになり得るのでしょうか?
安斎さん:
「自己実現」というキーワードを軸に考えてみると分かりやすいかもしれません。

多くの人が「自己実現=目標や夢を達成すること」だと考えがちですが、そうではないんですよね。内発的な動機(好奇心や興味)と、外発的な評価(お金や承認)が結びついたとき、人は充実感を得る。これが自己実現の理想的な状態です。
でも、この「内発的な動機と外発的な評価の一致」って、めちゃくちゃ儚くて、そう簡単には成立しない。ほとんどの人が、これを求め続けながら生きていると言っても過言ではないくらいに、なかなか結びつかないものなんです。

例えば、幼少期の「やりたいこと」と「評価されること」はズレがちですよね。子どもが「野球がしたい!」と言っても、「野球で食べていけるわけじゃないから勉強しろ」と言われたり、バンドを組んで「俺たちはこの音楽がやりたい」と思っても、売れる曲は別のジャンルだったりする。こうしたズレがずっと続いていくわけです。
でも、そんな中で、一部の人だけが、ある日突然「やりたいこと」と「評価されること」が結びつく瞬間を経験します。例えば、好きで続けていたことが3年後に評価されて仕事になったり、最初は気乗りしなかったけど、やっているうちに面白くなって評価されるようになったり。いずれにしても、粘り強く続けることで、この一致が生まれることがあるんですよね。
ご質問の答えとしては、「報酬」とは単にお金や評価を得ることではなく、外的な評価と内的な動機の結びつき方を探る機会なのではないか、と考えています。組織や仕事の場において、この結びつきを生み出す機会があるかどうかこそが、報酬だといえるのではないでしょうか。
河口さん:
僕もTEDxHamamatsuのオーガナイザーという役割をやっていますけど、たまに他の地域のTEDxイベントに行くときは、オーガナイザーの役割ではなく、例えばフォトチームに入ったりするんですよね。ある意味、報酬を求めて他のチームに参加するというか、「違う形での満足感を得るための活動」をしているんだと思います。
今のお話を聞いて、それってまさに「外的な評価と内的な動機の結びつき方を探る行動」なのかもしれないと思いました。
▼後編はこちら

